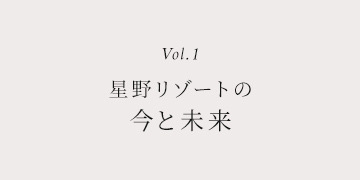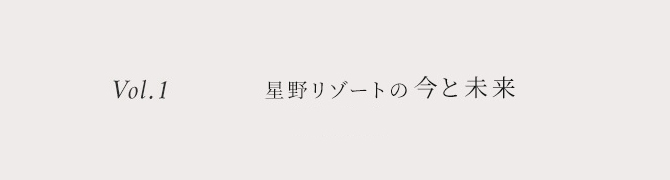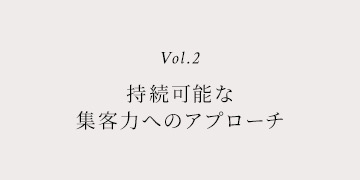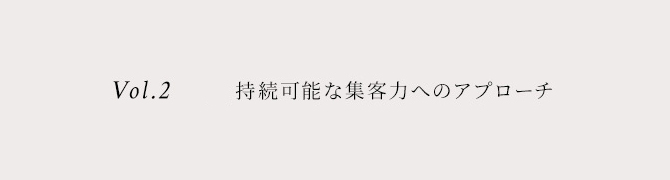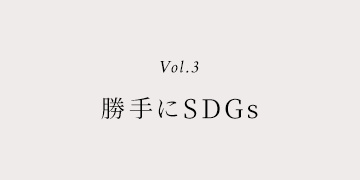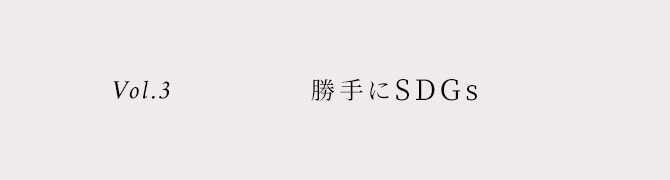私たちは、現代の経営学から学び、持続可能な競争力の獲得を目的に自社の改革を進めています。市場競争の中で新興勢力を含めた栄枯盛衰を繰り返した果てに、独自のポジションを確立する企業が持続性を維持し高い業績を保ち続けると考えています。しかし、競争環境の中でできあがったエコシステムも、約6,000万年前に巨大隕石が地球に衝突した時のように、一瞬にして有無を言わさず破壊される時があるのです。今回の新型コロナウィルスの登場をホテル経営の最前線で経験していると、そういうインパクトを感じます。それは、経営理論的に正しい姿が通用しない危機ということなのです。
約6,000万年前の隕石衝突は、大繁栄していた恐竜が支配する世界を一瞬で終わらせ、その後長い時間をかけて哺乳類が発達、そして私たちホモサピエンスが登場する原因をつくりました。さて、今回の新型コロナウィルスによるホテル需要の一時的な消滅は、観光産業にどういう変化を及ぼし、私たちはそれにどう対処すれば良いのでしょうか。
第一はホテル・リゾート業界におけるリスク概念の逆転が起こると考えています。私がホテル経営を学んだ1980年代後半、ホテルタイプに対するリスクの概念は、エアポートホテルが最も安定、次に都市ホテル、そしてリゾートは最もリスクが高いとされていました。リゾート分野は、不要不急の宿泊であり、旅行者本人が費用負担し、シーズナリティが激しく、災害時にも弱いのでリスクが高いのだと教わりました。しかし、リーマンショック、東日本大震災、そして今回の新型コロナウィルスといういくつかの危機を経験してみると、需要が最も安定しているのはリゾート分野であったと考えています。出張は、企業も旅行者も可能な限り避けたいと考えているのに対して、観光地への旅行は旅行者が自ら行きたいと考えているという動機の差が起因していると考えています。
変化に影響を与えてきたのはITテクノロジーの進化です。遠距離間のテレビ会議機能の進化は、ビジネストラベルの必要性を徐々に低下させていましたが、コロナ禍を契機に出張だけでなく、テレワークにより出勤のあり方も変わろうとしています。これは観光地・リゾートへの需要にはプラスになります。例えば、ある週の木曜日が祝日であった時、今までは観光需要には大きな影響は与えてきませんでした。しかし、金曜日だけリゾートから昼間テレワークで仕事することが許されると、水曜日の夜から日曜日まで4連泊滞在ができるようになるのです。コロナ禍による社会的変化の一つは、テレワークが市民権を得ようとしていることであります。今までは仕事の日と休みの日が明確に分かれていましたが、これからは観光地に滞在している日も仕事の日にすることができるようになります。
観光地・リゾート側もこの変化に急速に対応することになります。Wi-Fiの充実、テレワークによる会議参加の環境整備、連泊価格の設定、部屋清掃など連泊滞在サービスの見直し、そして食のバリエーション増加を含めた泊食分離の促進など、新しいニーズへの機能を素早く整える必要があります。星野リゾートの星のやは、すでにこのニーズの多くを満たす機能を備えています。温泉旅館の界、西洋型リゾートのリゾナーレにおいても対応を加速させていく計画です。

星野リゾートならではワーケーション
第二に、都市ホテルもビジネス客から都市観光客へのターゲットシフトを本気で行うことで、ポストコロナ時代にさらに成長する可能性があります。世界各都市の地域文化は強い観光資源であり、過去にも観光市場の多くを獲得してきたのは都市でありました。東京、大阪、京都だけでなく、日本の地方都市はそれぞれ独特な文化を持ち観光資源は豊かです。オンライン会議・テレワークが市民権を得る中で、都市への旅行者は出張ビジネス客から都市観光客へと益々シフトしていくと予測しており、「1人が寝るためのホテル」のあり方を大きく見直していく必要があると考えています。2018年に立ち上げたOMOブランドは、都市観光客に特化した最初のホテルブランドです。都市では観光地とは違って、魅力的な滞在コンテンツを提供する主役は街の中に存在しています。ホテル周辺で地域文化のコンテンツを提供する既存の事業者や個人と結びつき、一体となって顧客の滞在をデザインしていくことが求められます。コロナ禍においては、周辺の飲食店はテイクアウトを始め、経済活動が回復してくる時期にもソーシャルディスタンスを維持するために席数を半分にする必要が出てきています。ホテルは、顧客がテイクアウトしてきた地域の食を楽しむ場を提供する、出前機能を持つ飲食店にはホテル側から容易に発注できる機能を作るなどはお互いの課題を補完し合う要素があります。この時期はホテルと周辺事業者との新しい協力体制を作りやすく、その関係はコロナ危機後にも活かされます。
都市で主流であったグランドホテルは、館内の機能と周辺の機能が競合する時に、館内に「持ち込まれること」に対して否定的な対応をしてきました。それはホテル滞在時の常識として浸透しており、顧客は遠慮しながら持ち込んでいます。ホテル内の飲食機能を含めたサービスの収益性は低く、サービスと部屋面積を必要最低限まで削ぎ落としたリミテッドサービスホテルが誕生してきたのです。しかし、都市観光客のニーズは、面積・機能を含めて快適な客室に滞在し、都市機能を満喫するための自由、そして滞在をサポートしてくれるホテルのサービスであるのです。これらのニーズに、ホテルに先駆けて応えてきたのが民泊です。Airbnbの急成長は、市場を創造した結果ではなく、既存のホテルが旅行市場のニーズ変化に応えてこなかった結果なのです。民泊利用者は民泊で100%満足しているわけではありません。民泊のベネフィットとパブリックエリアやオンサイトの人的対応を含めたホテルサービスが融合されることを期待しています。
都市観光客をターゲットとするOMOは、周辺のレストランや店舗と積極的な連携を模索し、今までのホテル文化にこだわらないサービスを展開しています。今後のOMOの開発と進化においては、民泊の顧客ベネフィットを完全に取り込む計画を進めています。
20代の若者をターゲットにした新しいホテルブランドBEBでは、持ち込みを初めて積極的に奨励するサービスを開始し評価されています。テイクアウトしてきた飲食を遠慮しながら部屋に持ち込むのではなく、新たなパブリック機能として「タマリバ」を作り、自由に楽しんでいただくことができる空間を設定したことが成果をあげています。
結論としてコロナ危機は、約6,000万年前の隕石衝突とはだいぶ異なり、想定外の変化を生み出そうとしているのではなく、過去の流れ、そして想定されていた旅行市場の変化を加速させると考えています。この危機をまず乗り越えることが重要ではありますが、人材と財務体力を温存したまま乗り越え、加速するニーズ変化に一気に対応することが市場を征することにつながると考えています。