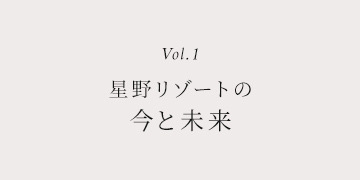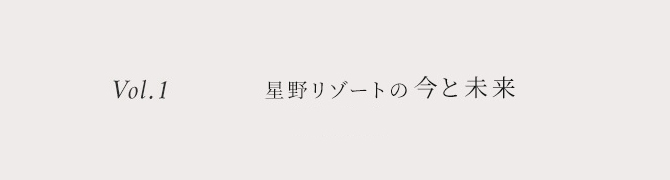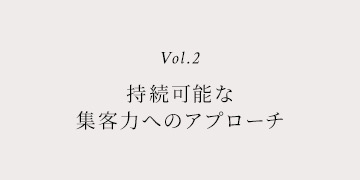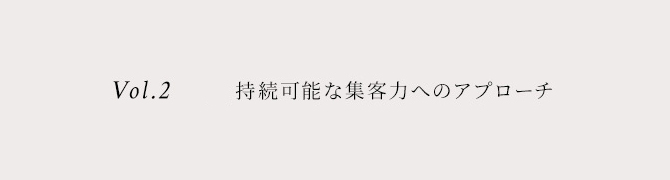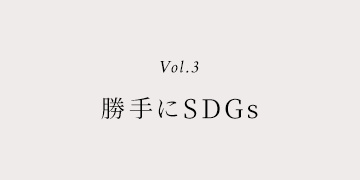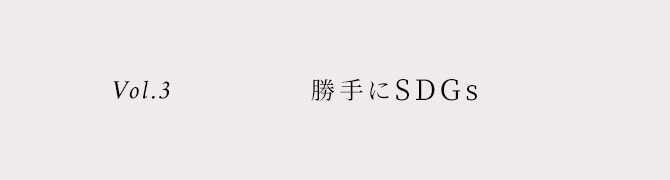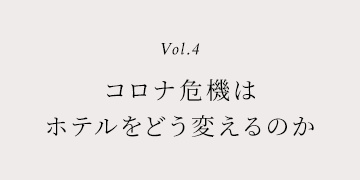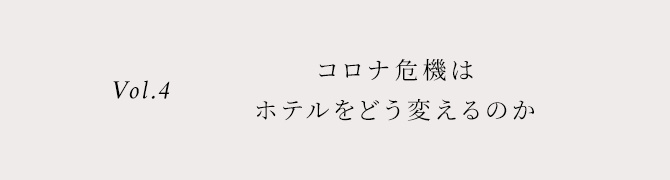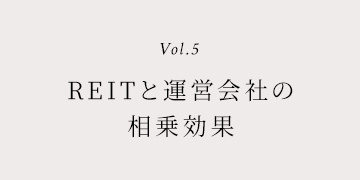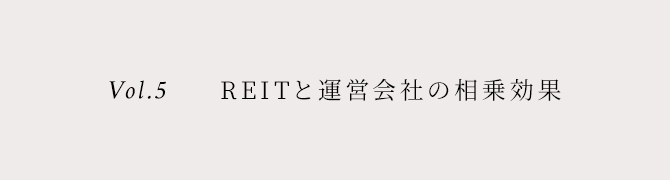星野リゾートは、ポストコロナを見据えた取り組みを始めています。その中の一つにインバウンド復活に向けた活動があります。今回は、なぜインバウンドが日本にとって重要なのかについてお伝えしたいと思います。前半で経済面について述べますが、後半では観光産業の社会的使命と国際観光との関係について記述し、ESG投資が進む世界で観光が注目されるポイントを考察します。
インバウンドの経済的価値
日本の観光産業の消費額は28兆円と大きく、これは国内で5番目に大きな産業規模です。その中でインバウンドが占める割合はまだ17%程度であり、コロナ危機においては83%の日本人市場が観光産業を支えてくれました。しかし、ポストコロナに向けては再びインバウンドの成長が注目されると予測しています。それにはいくつかの理由があるのです。
第一の理由は、成長市場であるということ。世界では新興国を中心に中間層人口が増加しており、それは国際観光市場の拡大を意味しています。日本のインバウンド市場もコロナ前の15年間順調に成長してきましたが、その理由は、日本の観光産業が諸外国に比べて強かったからという以上に、世界中で外国旅行をする人口が増えていたという点が大きく貢献しました。世界での国際観光市場における競争はこれからであり、日本はこの成長市場を逃さないように自らを変革していく必要があります。
インバウンドが注目される第二の理由は、日本にとっての重要性です。日本の人口は2008年をピークに減少に転じており、2030年には1億1912万人になると推計されており、今後毎年60万人以上のペースで減少していきます。1人減ると年間消費額は127万円減少するのですが、これはインバウンド8人を増やすことで相殺することができます。もちろん、これだけで人口減少問題が解決するわけではありませんが、インバウンド増加は重要な対策の一つになると考えられています。
インバウンドは、海外の方々に日本のサービスを買っていただくという産業であり、輸出に分類されます。2019年のインバウンド市場規模の4.8兆円は、日本の輸出産業の中でもすでに3番目に大きな規模になっています。過去に製造業の工場が海外移転し地方経済にとって課題になったことがありましたが、有名観光地は「人件費が安い」ぐらいの理由で海外移転したりしないので、長期的に安定した経済基盤になることでも期待されているのです。
観光産業の課題
その中で課題も沢山あります。第一は、観光産業の低生産性。市場規模が大きくても生み出す収益、そして価値が少なければ経済効果としては十分ではありません。大きな国内需要が一部の日に集中することによる繁閑の差は、観光産業の低収益構造の原因です。その結果、7割以上が非正規雇用、低い人材の定着率、投資力の不足などにつながっています。私が以前から提言している解決策は、巨大な国内需要が健全なうちにこれを平準化し生産性を上げるというものです。その結果人材と設備への投資を促進し、国際旅行市場での競争に備えるということであり、具体的には大型連休の地域別取得を提言してきました。これは、フランスなどの観光先進国ではすでに制度化されていることでもあります。
星野リゾートは、これらの問題には独自で対処してきました。温泉旅館に完全なマルチタスクシステムを導入したことにより、労働生産性を上げ、必要人員のほぼ全員を正社員化することを達成しています。収益率の向上は職場環境の改善と設備面への投資を可能にし、現代の旅行市場のニーズに応えることができる施設を増やしてきています。
日本の観光産業第二の課題はインバウンド格差です。前述したように、観光産業は人口減少が進む地方の経済において新しい産業基盤になることを一つの目標にし、インバウンドにも積極的に取り組んできました。しかし、現状は東京、京都、大阪、北海道などのトップ10都道府県でインバウンドの80%以上を集客していて、37県にはまだその経済効果は発生していません。つまり、当初の目論見とは違った姿になっているということなのです。インバウンドを一過性のブームで終わらせないためにも、日本の地方に足を運んでいただくインバウンド・マーケティングが重要になってくると考えています。
観光産業の社会的役割
インバウンドを含む国際観光は、経済的な側面とともに、ソーシャルな側面で重要な役割を担っています。2003年小泉内閣の政策の一つとして「観光立国を目指す」という方針が打ち出され、現在につながる様々な取り組みがスタートしました。この観光立国という言葉、実ははるか以前から存在していました。初めて登場したのは、1954年4月号の文藝春秋誌に掲載された松下幸之助の論文でした。そこには今に通じる多くの示唆があるのですが、私が特に注目しているのは松下幸之助が「観光は最も大きな平和方策である」と主張したことです。製品を輸出しても日本を好きにはならないが、旅してもらうと日本を好きになってもらえる。それはお互いの相互理解につながり、結果的に平和に通じるということなのです。国と国との関係においては政治が果たす役割が大きいのは事実ですが、政治も世論をみて判断しているのですから、民間レベルの相互理解を深める効果がある国際観光は平和促進の活動なのです。
「観光への投資は平和への投資である」、この崇高な使命は、星野リゾート全てのスタッフのモチベーションを高めてくれます。同時に思うことは、決してインバウンドだけが大事なのではなく、アウトバウンド(日本人の海外旅行)も同じく大事であるということです。世界の方々に日本各地を旅してもらい、この国を理解し好きになって欲しい。そして私たちも世界を旅して他国の地域や文化を理解する、そういうことが長期的に平和をつくっていくのだと考えています。
でも、本当に旅をすると日本を好きになるのでしょうか?その前提が崩れてしまうと大変です。星野リゾートは2014年、創業100周年記念事業として世界から100人の若者を募集し、日本の旅をプレゼントしました。それは、日本を初めて訪れる若者が本当に日本を好きになったのかを確認するプロジェクトでした。世界中から応募があり、参加してくれた120名の日本旅を「100Trip Stories」として記録に残しています。この機会に是非ご覧ください。
- (注1)
- データは、総務省統計局 労働力調査(2019年度)/国土交通省観光白書(令和2年版)/国立社会保障・人口問題研究所『人口統計資料集2018』より
- (注2)
- このページの内容は2021年7月28日でのものです。


https://www.hoshinoresorts.com/100stories/

星のや軽井沢