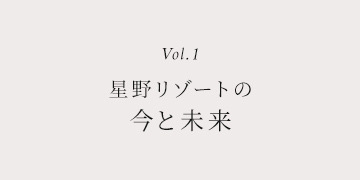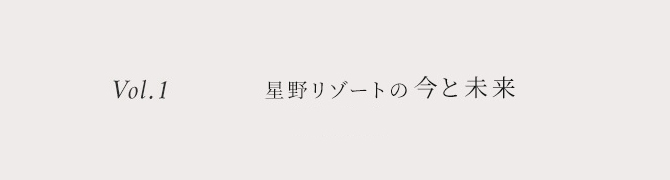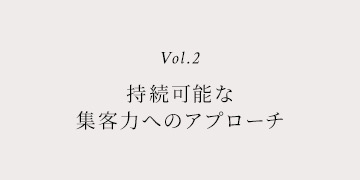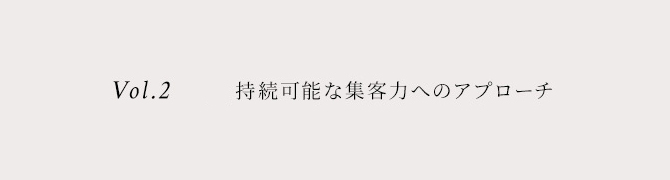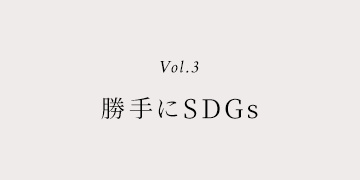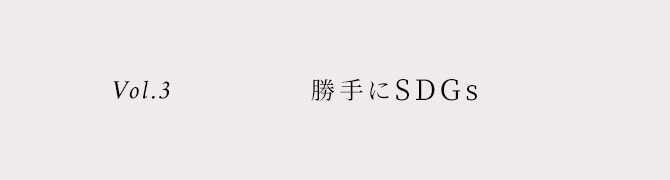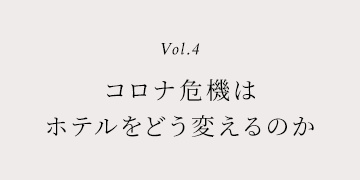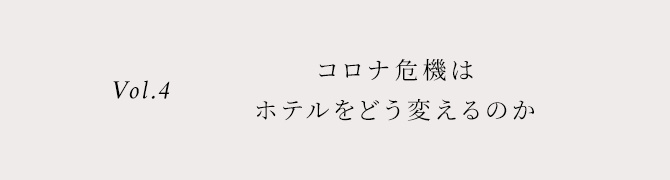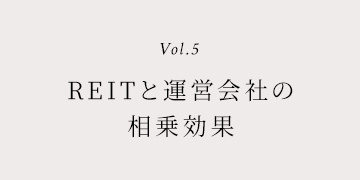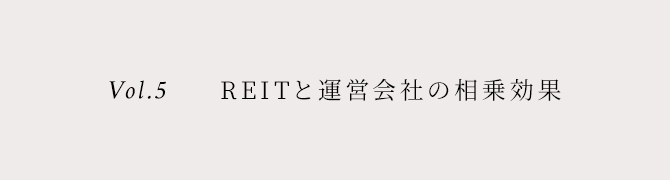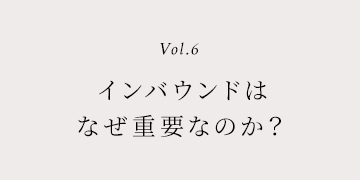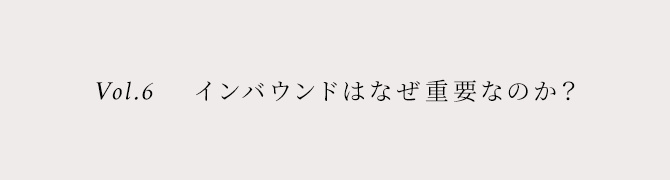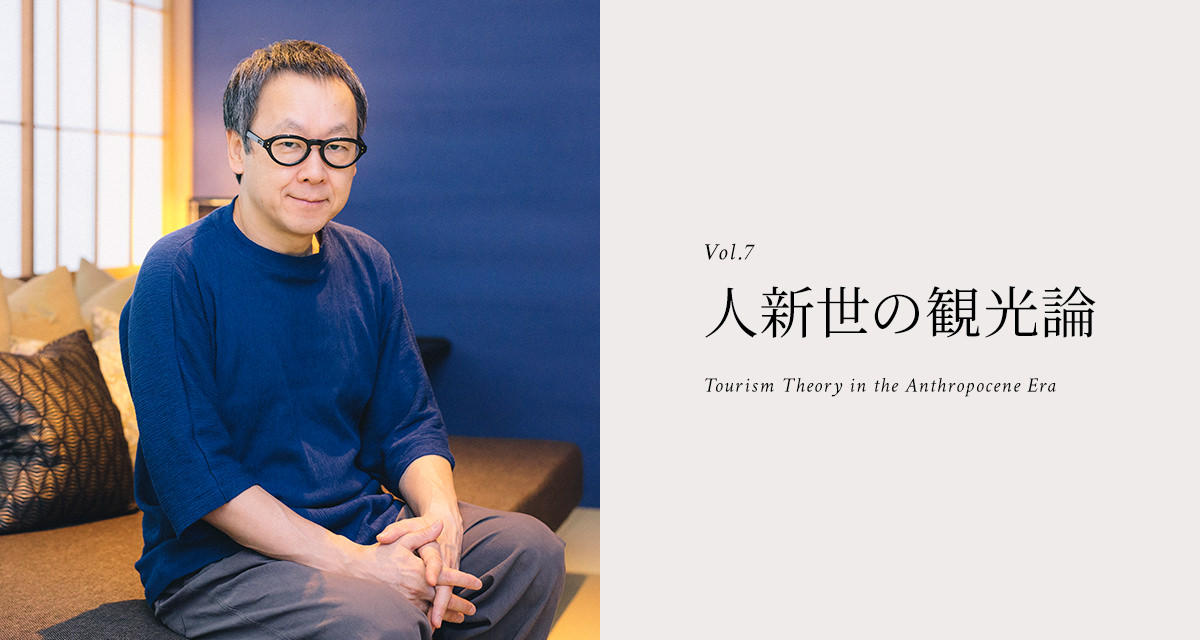

コロナ禍は、今後も紆余曲折しながらも全体として終息に向かい、2022年の日本人による日本国内観光は回復に向かうと考えている。2019年の国内市場の国内旅行消費額は22兆円、海外旅行消費額は約3兆円あると推測しており、25兆円の潜在力がある大きな市場だ。
マイクロツーリズム(自宅から3時間圏内の旅行)はコロナ禍においても動いた。COVID19の感染拡大が深刻化しやすい大都市圏からの旅行市場に依存し過ぎていることはリスクだ。マイクロツーリズム市場から一定の需要を確保し、広い地域に施設展開していることで地域ごとの需要差に組織として最適化しリスク回避につなげることができた。ここでもマルチタスクが大きく貢献した。界箱根のスタッフは、界別府に行っても、施設の差を理解するだけでトレーニングなしで仕事に入ることができる。
星野リゾートは、マイクロツーリズム市場に対するアプローチをコロナ禍で継続的に進化させてきた。全国を11のマイクロツーリズム商圏に分け、商圏ごとに地元向けの魅力を発想し、情報が潜在旅行者に届く方法を新たに採用した。例えば、コロナ禍で情報掲載量が落ちていた地域媒体の方々と協力しあい、マイクロツーリズム向けの魅力と価格を掲載し、各商圏ごとに用意した予約ランディングサイトにQRコードを通して効率的に誘導した。郵便番号を利用して正しい商圏からの市場であることを判別するシステムも構築した。
マイクロツーリズム市場からの集客の仕組みはコロナ禍後も維持したいと考えている。次の危機対応に備えるだけではなく、オフシーズン対策、平日対策にも有効であることがわかった。この活動を通して改めて認識したことは、予約獲得の仕組みを、変化し続ける環境にアジャイル対応させることの重要性だ。そのためには、社内のシステム開発チーム、運営チーム、そしてマーケティングチームが一体となって課題解決方法をさぐり、必要なリソースを素早く調達する柔軟な組織が必要である。「一体」「素早く」「柔軟」、これらの要素を組織に自然に発揮させているのがフラットな組織文化である。ケン・ブランチャード理論の実践は星野リゾートの競争力の源泉だ。
「過去30年においてホテル業界で最も変化したことは何か」と尋ねられると、私は迷わず「予約方法」と答える。父の温泉旅館を引き継いだ時には、大手旅行代理店からのファックスと顧客からの電話という2つの予約受付方法しかなかった。この2つは今では全体の2割以下となり、8割はオンライン、それもスマートフォンから入ってくるようになった。星野リゾートの特徴として、ブランド戦略の展開やマルチタスクに代表される運営の仕組みが目立つが、もう一つ重要な要素は予約獲得方法の独自進化だと考えている。ヤドゲッツというコードネームの予約システムを、長い時間をかけて淡々と進化させ、現在はヤドゲッツ3.5、そして今最も優先して取り組んでいるのはヤドゲッツ4.0へのアジャイル進化だ。私にとってこれは長い間夢見てきた世界であり、それは旅行者にとって理想の予約体験になると確信している。同時にそれは、予約システムと施設運営を一体として行っていない限り不可能な機能が満載されており、市場における星野リゾートの競争優位につながると考えている。例えば、星のや軽井沢には大きくわけると3タイプの部屋が77室あるが、1タイプの中にも景色やロケーションなどそれぞれに個性がある。オンラインでの部屋指定予約のニーズは確実にあり、特にリピーターには高いはずだ。航空会社にできていることがまだ宿泊施設にはできていないのである。
注目されているインバウンドの戻りは、ゆっくりと確実にやってくると予測している。2025年の大阪万国博覧会は国家的イベントであり、成否の基準は入場者数だ。イベントの成功、そしてその成果を次のインバウンド需要につなげることが日本観光にとっての命題だ。2022年から24年までは助走期間であり、この3年間で2019年比で100%まで戻していくことができると、万国博覧会の成功が視野に入ってくる。日本の観光政策はそういう目標をたてて進むことになるだろう。2019年のインバウンドは3,188万人と過去最高であったが、消費額は4.8兆円であり、国内市場の25兆円に比べると少ない。(注1)インバウンド市場が戻ってくるということは、アウトバウンド市場(日本人の海外旅行)も復活することを意味しており、2019年の数字でいえば、4.8兆円が戻り始めると、3.0兆円が海外に流出し始めるということでもある。したがって焦ることなく着実に、2025年の大阪万国博覧会に向けて助走していくことで良いはずだ。
助走期間における星野リゾートの重要戦略は、都市観光ホテルブランド「OMO(おも)」の展開スピードを速め、2025年には、星のや、界、リゾナーレに負けないブランドに成長させることである。2021年に4施設開業、2022年にはOMO7大阪を含め発表済みの案件で4施設を開業(注2)、さらにスピードを高めていきたい。過去のケースでもそうであったように、ホテル市況が悪化する局面においては運営会社の実力が重視される傾向があり、コロナ禍において星野リゾートの運営施設数は伸びている。このチャンスを捉え、ホテル投資家のニーズに応えるためには、更なる観光人材の確保と育成が急務であり、星野リゾートは2022年4月に681名の新卒入社が確定しており、欧米の観光産業で起こっているような人員不足状態は発生しない。

OMO7大阪(2022年4月開業予定)
先日、「人新世の資本論」の著者である斎藤幸平先生と対談させていただく機会を得た。私の価値観は、本書の骨子と共有する部分が多々あるが、成長のプロフェッショナルである経営者が「脱成長」にどう向き合うことができるのかという興味から、私からお願いして時間を割いていただいた。対談は私にとってエキサイティングな時間となり、今後の旅産業が向かうべき方向性を発見することができた。
発見は2つだ。第一は、マイクロツーリズムの推進は脱成長であるということ。今まで私たちはより遠くに旅行していただくことを模索してきた。決して遠い場所への旅を否定するものでもないが、もし同じレベルの旅の効能を自宅から3時間圏内で提供することができれば、それは温室効果ガスの減少に大きな貢献となる。「旅行は海外しか行かない」という市場がコロナ禍で国内の星野リゾートをご利用になり、高い評価をいただく機会を得た。そういう方々にコロナ禍後も旅行機会の半分を国内の観光地に変えていただき、旅の効能は海外旅行よりも高いと評価いただくサービスを提供することができれば、それは私たちにとって大きな成長であり、斎藤先生の地球レベルの視点では脱成長なのだ。
第二は、連泊する滞在型への変革は脱成長であるということ。年10泊の旅行をする家族を想定してみよう。1泊2食の旅を10回するよりも、1回5泊の旅を年2回していただく方が環境負荷を下げることができる。移動で発生する温室効果ガスだけではなく、リネンのクリーニング回数の減少など滞在中の環境負荷も下げる余地が生まれてくる。移動回数の減少は、旅行者にとって1泊当たりのコスト負担を大きく減少させる。宿泊施設の視点では、チェックイン・アウト数の減少による効率化、同じ売上を確保するための予約数の減少によるマーケティングコストの低下、など生産性が高まり、価格をさらに下げることにつながる。つまり、滞在型への変革は、環境負荷を低減させながら、同じ費用負担で年10泊を14泊、またはそれ以上の旅にすることができる。これも観光産業にとって成長であり、斎藤先生の地球規模の視点では脱成長なのである。対談の結果、新しい方向性が突如誕生したわけではないが、やっていることのやるべき理由が強化され、何よりも私のやる気が妙に増してきたのである。

星のや軽井沢
- (注1)
- 令和2年版「観光白書」(国土交通省)より
- (注2)
- 本頁で紹介している施設で、本投資法人の保有物件でない施設については、現時点で本投資法人で取得する予定も、決定している事実もありません。