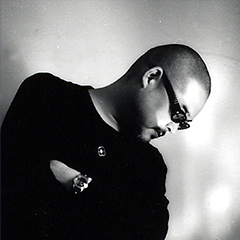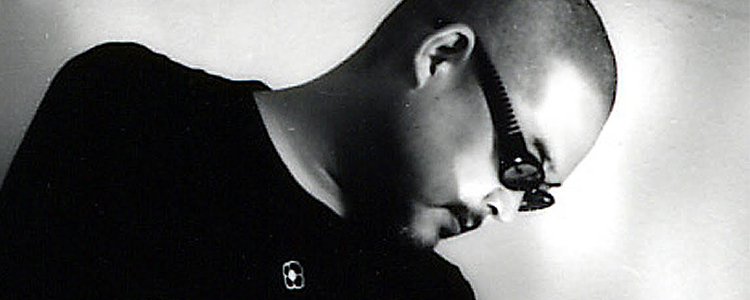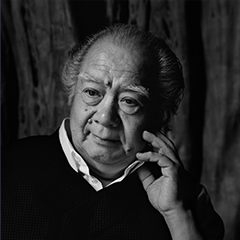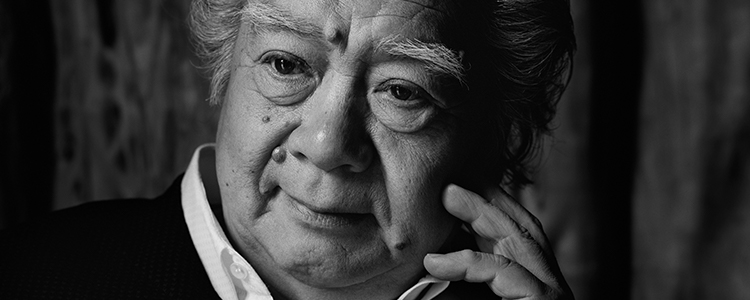価値を
創る。
想いをかたどり、価値へ変える、共創者たち。
Vol.2

Astrid Klein
アストリッド・クライン(左)
Astrid Klein
Yukinari Hisayama
久山 幸成(中)
Yukinari Hisayama
Mark Dytham
マーク・ダイサム(右)
Mark Dytham
クライン ダイサム アーキテクツ
マスプロダクションから
感動は生まれません。
建築やインテリア、インスタレーションまで、幅広い分野のデザインを手がける「クライン ダイサム アーキテクツ」。その中心人物でもあるアストリッド・クライン氏とマーク・ダイサム氏、そして久山幸成氏の3名に、ユニークな経験を生む思考を伺いました。
ユニークであり、
タイムレスなデザインこそ美しい。
アストリッド・クライン(以下、クライン)「私たちはデザインする立場にいますが、常に自分がその施設を利用するお客様だとイメージして、顧客視点から考えます。『自分だったら、どんな場所に泊まりたいのか』『自分だったら、そこで何をしたいのか』というようにです。運営側の都合だけを聞いていては見えてこない、『お客様はもっとこんなことを求めているでしょ』というものが、必ず見つかります」
久山幸成(以下、久山)「そしてこれまでにないものをつくりたい、新しいことにチャレンジしたいという考えが、根っこにはいつもあります」
マーク・ダイサム(以下、ダイサム)「星野リゾートとの仕事は、〈リゾナーレ八ヶ岳〉のガーデンチャペル『ZONA』をデザインすることから始まりましたが、その時のオーダーが『これまでにないチャペルを』ということで、私たちもそう望んでいたし、非常に楽しめました」
久山「当時のブライダルでは、新郎新婦がゴンドラに乗って降りてくるような演出が散見されていたのですが、そうしたギミックな装置は建築とは関係なかったり、お客様の趣味や嗜好に合ったものではないのが実情でした。ウェディング専用のチャペルをデザインするときには、挙式の一連の流れを意味のあるものにしたかったのです。『何かおかしい』と感じることをピックアップしながら、それらをどう素敵なものにできるか考えたのです」
クライン「基本的に、建築をつくるには膨大な費用がかかります。ファッショナブルな建築は、一見とても華やかに映りますが、多大な投資をしてつくっても、翌年には時代遅れのものになってしまう。そうなると、オーナーや運営者は困りますよね。ギミックをつくったとしても、それはまるで一発芸のよう。一方で“タイムレスなもの”、つまり時代性を問わないものは、いつでも美しいと感じます。真に意味があり、意味の中に美しさのある建物。そうした美しさが、タイムレスな魅力につながります」
久山「とんでもないものは、つくろうと思えば簡単につくることができます。ユニークさは必要ですが、無理矢理では意味がない。私たちはある側面で“当たり前さ”を目指しているところがあるんです。でもそれだけを考えていると、つまらなくなる。まずは楽しめるか、ユニークかどうかから発想し、その後にタイムレスなものなのか、視点を一度引き戻してみる。ユニークとタイムレスの二軸の思考を、行ったり来たりしながらデザインしている感覚です」
クライン「あと私たちがデザインを考えるときは、何を面白いと思っているのか、スタッフと話し合いながら進めます。フラットな関係でみんながアイデアを持ち寄って、スケッチを交えたりしながら。誰が出したアイデアか覚えていないプロジェクトもたくさんありますよ。プロセスの中で、アイデアはどんどん進化していきますから」
久山「そうすると、話し合っていく中で『これならみんなで盛り上がれるな』というアイデアがどこからか出てきます。スタートするときは皆が違う視点だったのに、同じ方向を向ける強力なキーワードやコンセプトが生まれるのです。そうすれば自分たちだけでなく、いろんな人もこのキーワードやコンセプトで盛り上がれるのではないか、と。そのアイデアのコアをなるべく強くしていくのです」
クライン「そう、リニアなプロセスではありません。最初はミストのように形が見えず掴むこともできない無数のアイデアですが、そのミストがだんだんと水滴になっていくようなプロセスなのです。それはまるでウイスキーの蒸留のような工程です」
ダイサム「それに、さほどロジカルではないかもしれません。もちろんロジックはあるのですが」
久山「最後にできたものには必ず理由があるのですが、その理由となるロジックは『ロジカルシンキング』という言葉で使われる『ロジカル』のニュアンスとは違うのですね。ロジカルシンキングは言葉で説明、理解できるものですが、良いアイデアはどこか感覚的な部分でみんながいいと思うところもあるのです」

マスプロダクションから、感動は生まれません。
クライン「最近、日本のホテル業界は、ちょっと堅い雰囲気になっているなと感じています。そんな空気感だからこそ、もっとフレキシビリティを持って、何が楽しいのかを一所懸命に考えながらつくりたい。楽しさって、客室の大きさや、どのくらいラグジュアリーなのかではなく、経験なのです。そこでしか味わえない、スペシャルな経験。何かちょっと驚きがあったり、ウィットに富んでいるくらいのほうがいいですよね。ホテルで滞在する時間は比較的短いので、わりと極端なことができます。それをうまく捉えてデザインできたらいいなと思います。例えば、空間に普段は見ないような色や大胆なグラフィックを取り入れることも面白いですよね。〈リゾナーレ八ヶ岳〉の客室には、1つの壁面に八ヶ岳をテーマにしたグラフィックをあしらいました。八ヶ岳のエリアに住んでいる人にとっては必要ないかもしれませんが、泊まる人にとっては八ヶ岳のグラフィックは面白いと感じます。これは他の場所ではできませんし、ローカルネスにもつながります」
久山「綺麗な部屋はどこでもつくれますが、その場所にしかできないことを考えて、周辺とつながることは何かつくりたいと思っています」
クライン「だから経験が楽しさにつながると考えているホテルには、私たちもすごく共感しますね。〈リゾナーレ熱海〉でも、『海と空』や『花火』など、熱海に関連した特徴を、できるだけ取り出して表現しました」
ダイサム「地域性と経験を重ねて、ローカルに対してもインパクトのあることをしたいと思っています。私たちも建築だけでなく、全体のブランディングはよく考えますね」
クライン「何か持ち帰ることができるようなメッセージが1つあると、いいですよね。人の心に響く何かがつながっていけば、メッセージはより強くなる。宿泊先から家に戻って、日常生活に戻ったときでも、そうしたイメージが伝わってくることはすごく大切です。だからユニークであることやアイコニックであることは、とても大事なこと。一般的な床や壁、天井とは、少し差をつけたいのですよね。何か思い出になるような、心が動かされて、エモーショナルなことは、今の時代に大切なのではないでしょうか。周りを見渡せば、みんなすごく忙しくて、本当に楽しんでいるのかな?と感じます。良いものを見て、家に帰って『何かよかったね』と言って、またそこに行きたくなったり、クチコミで家族や友達に伝わったり。普通のオフィスビルでは、そんな思いが生まれたり循環は起こりませんよね」
久山「熱海では毎月のように花火が打ち上げられているのに、花火をフィーチャーしている宿泊施設はなかったと思います。和食ダイニングでは花火をテーマにしたブースがしつらえてあることで、宿泊者は花火が開催されていることを発見することにもなります」
クライン「花火をイメージしたブースは、色を手作業で付けてもらったりと、だいぶ苦労しました。でも大量生産品ではなく、クラフト感があるからこそ、見る人にも何か感じてもらえると思っています。マスプロダクションでは、この感情は生まれません」
久山「利用者が見た瞬間のダイレクトな反応は、大事だと思っています。一般の方は専門知識などがない状態で直感的に受け取り、自分が楽しんだかどうか、すごいと思ったかどうかだけが記憶に残るはずですから。宿泊した人が驚いて、また花火のある時に行こうかなと思っていただけると、街にとってもWIN-WINなのかなと思います」

これからデザインしたいこと、
これからのデザインに求められること。
クライン「いま興味があるのは、もっと楽しく暮らすということ。ほとんどの人が戸建住宅やマンションに住んでいるのですが、どうも自分中心でしか暮らせていないように見えます。たまにはお隣さんと夕飯を一緒に食べたい、週末にバーベキューしたい、なんて思うこともあるでしょう。私は料理をするのはあまり好きでないのですが、料理が好きな人もいます。そんなとき、共有のキッチンがあるような、一緒に暮らして集まることができるマンションがあったらいいと思います。福島県相馬市が設置者である〈相馬 こどものみんなの家〉の設計に携わり、いつも誰かがいて、何かをしているという場所があることの大切さに気づきました。子どもが放課後に立ち寄って宿題をしたり、そこにはおじいさんやおばあさんがいたり、どこか楽しい場所になっている。そうしたコミュニティが生まれるスペースを、これからの建築はもっと取り入れたほうがいい。今のマンションの管理費をどう振り分けるかなど考えなければいけないことはたくさんありますが、もしこんなスペースがあれば、一人暮らしの若者がメンタル的に弱くなったときに、他の誰かが相談に乗ってあげられるかもしれません。そうした暮らしは、今よりも充実するのではないかと思うのです」
ダイサム「私は、全国で新しい形態のホテルチェーンをつくり出したいですね。日本全国には素晴らしい景色を持つ素敵な場所がたくさんあるのですが、ホテルはごく普通で残念というところも少なくありません。それで、ちょっと素敵でミレニアルなデザインのホテルがあったらいいなと。休暇を過ごすだけではなく、ワークスペースとして1週間くらい滞在することもできるでしょう。これを実現できるポテンシャルが、日本にはあるのです」
クライン「それはいいね。イタリアでは『ヴィレッジホテル』といって、高齢化の進んだ小さな村全体をホテルのようにしたところがたくさんあります。1戸の家は受付やカフェとして機能し、泊まるのは他の家で、というスタイル」
久山「街や村という話にもつながりますが、私は商店街をつくりたいと思っています。どうやったら、衰退している街を盛り上げられるか。すでに地方都市では若い人が『商店街ホテル』というものを空き家を利用して始めているようですが、これからは日本人だけが訪れるわけではありませんから、もっといろんなことができるだろうなと思います。ローカルの人たちと、どう新しい街をつくることができるか。ポジティブに取り組めたら、いろいろと面白いだろうなと思います」
ダイサム「ホテルだけでなくて、私たちがずっと運営してきた『スーパーデラックス』のように、ライブもギャラリーもできるミックスしたスペースがあるといいですね。海外からの旅行者もスマートフォンがあることで、以前よりずっと宿泊予約や移動がしやすくなっているし」
クライン「ミレニアル世代は、もう旧態依然なラグジュアリーという価値観に興味がなく、経験に重きを置いています。経験こそが、ニューラグジュアリーとなる。これから私たちがデザインするものでも、経験をキュレーションしていくことは大事にしていこうと思っています」

福島県相馬市の「相馬 こどものみんなの家」の設計を担当。©Koichi Torimura
Profile
建築、インテリア、家具、インスタレーション、イベントといった複数の分野のデザインを手掛けるマルチリンガルな設計オフィス。RCAを修了したアストリッド・クラインとマーク・ダイサムにより1991年に設立。国際的評価も高く、Design for Asia、World Architecture Festival、Wallpaper Design Awardなど受賞多数。現在世界約1,100都市以上で開催されるクリエイティブイベント「PechaKucha Night」の創設者でもある。
- 代表作
- 代官山T-SITE/蔦屋書店 (2011)/GINZA PLACE(2016)/Open House(バンコク, 2017)